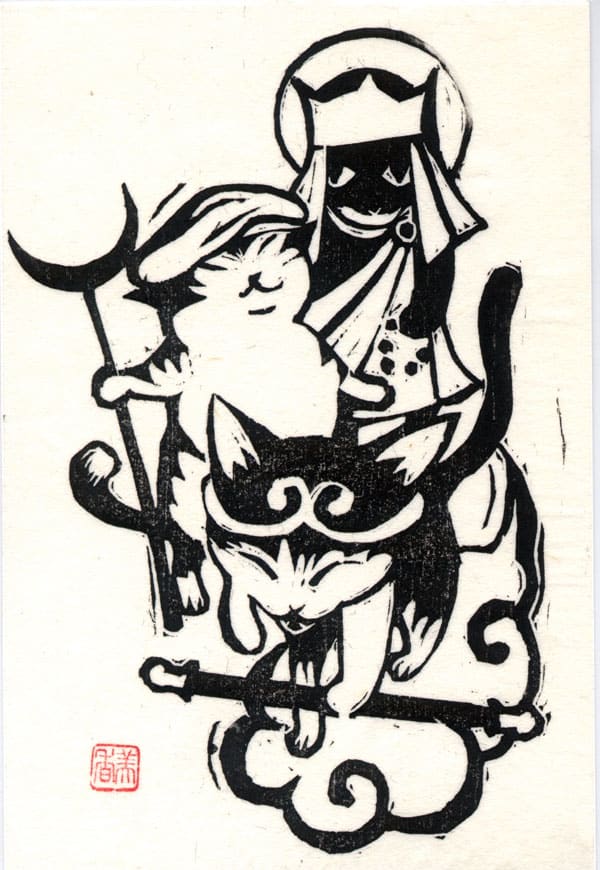いただきものの立派な夏みかん。
下に転がっているのは
生徒さんがわざわざ秋田から取り寄せているという
美味しい美味しい干し柿。
ちゃんとお日様に干しているからとっても甘く
白い粉もたっぷり吹いてる。
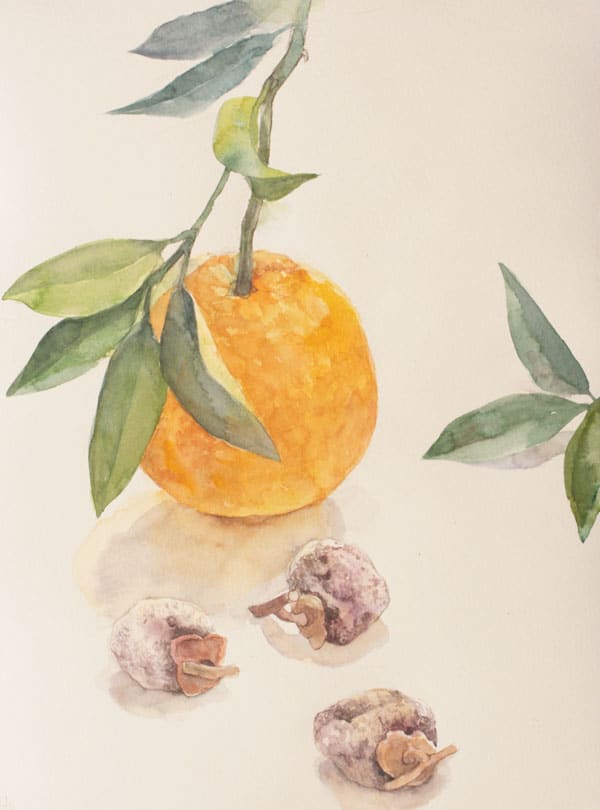
今年は自家製干し柿を半分ほどダメにしてしまった。
秋の前半はお天気つづきでからりとうまく乾き
美味しい干し柿ができてたっぷりいただいた。
ところが後半、雨続き。
おまけに気温もそんなに下がらなかったものだから
いっぺんにカビてしまったのだった。
とても残念。
ちなみにこのプロの方の作った干し柿が
こんなに粉吹いているのは麹のおかげなのだそう。
だからたとえばもうできてる干し柿や干し芋など、
すでに粉の吹いたものをそばにおいておくと
あたらしく干し始めた柿も粉を吹くのだそうだ。
今度の秋はぜひためしてみたい。
ナツミカン(夏蜜柑)
学名:Citrus natsudaidai
科名:ミカン科ミカン属
別名:ナツカン(夏柑)、ナツダイダイ(夏橙)
夏橙(なつだいだい)が正式な名称。1700年頃(江戸時代中期)
現在の山口県長門市の青海島、大日比海岸に漂着したかんきつの種
子を西本於長という女性が播いたのが起源。
その原木は昭和2年4月8日に史跡名勝天然記念物に指定され
現在でも、西本家の庭で保存されている。
夏みかんはもともと秋に実がなる果物だったが
あまりに酸っぱくそのままでは食べられるものではなかったため
酢の代用品として使われてきたが、そのまま取らずに初夏頃までおくと
酸味が和らぎみかんのようにおいしく食べられることが分かり
夏みかんと呼ばれるようになった。